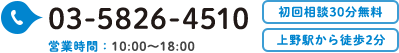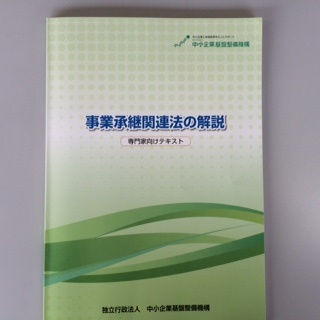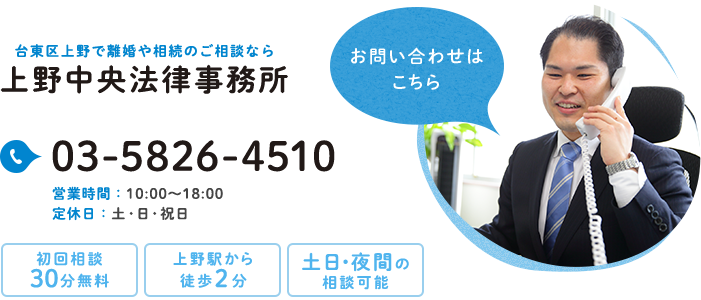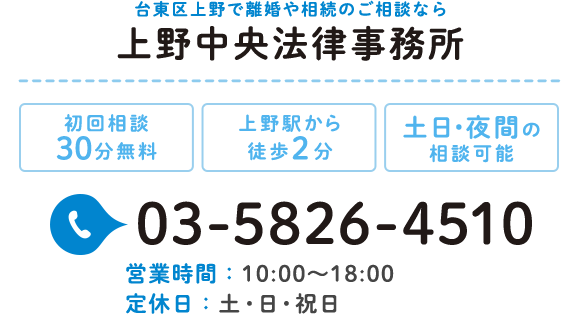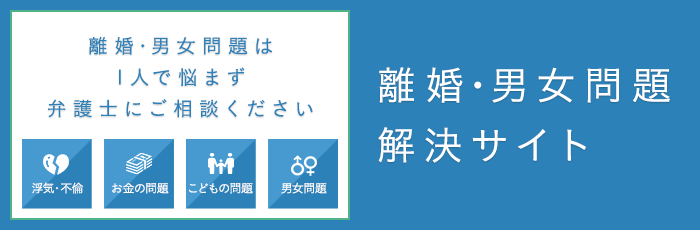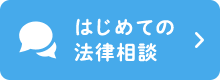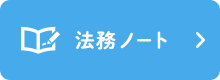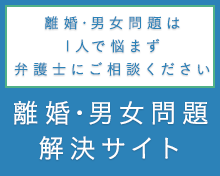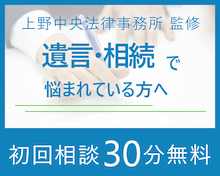【相続】相続放棄の手続は、自分でできる?
2016.05.20更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
◆質問
「相続放棄の手続は、
弁護士に依頼せずに自分でできますか?」
◇回答
結論からお話します。
相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)は、
法律上は、
弁護士にしかできないということはありません。
ご相談者がご自身で手続できます。
ただ、
相続放棄申述には、
相続放棄申述書や
戸籍謄本などの添付書類を
提出する必要があります。
相続放棄の手続を
スムーズにすすめるためには、
弁護士などの専門家に依頼することを
おすすめします。
相続放棄でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
遺言・相続は初回相談無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者: